No.060
Issued: 2016.12.20
東京大学大気海洋研究所・木本昌秀教授に聞く、異常気象のメカニズム、そして地球温暖化との関係

実施日時:平成28年11月22日(火)14:30〜
ゲスト:木本 昌秀(きもと まさひで)さん
聞き手:一般財団法人環境イノベーション情報機構 理事長 大塚柳太郎
- 東京大学大気海洋研究所 副所長・教授
- 気候システム研究系系長
- さまざまな時間スケールの気候変動を理解し、予測することを目標に研究を行っている。
- 複雑多様な気候変動現象を理解し、ひいては予測するために、それらを再現できる数値気候モデルの開発が重要であると考えており、多くの研究者と協力して世界トップレベルの大気海洋結合気候モデルの開発を進めている。
自然の現象として、気象には揺らぎがあるのが本来の性質
大塚理事長(以下、大塚)― エコチャレンジャーにお出ましいただきありがとうございます。
木本さんは、気象庁気象研究所研究官を経て、現在は東京大学大気海洋研究所教授として気象学の研究と次世代の研究者の育成に携わっておられます。また、気象庁の異常気象分析検討会会長、環境省の中央環境審議会気候変動影響評価等小委員会専門委員などとして活躍されておられます。本日は、最近大きな関心を集めている異常気象について、そのメカニズムや地球温暖化との関係などを含め、お話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
今日は、日本古来の季節感を表す二十四節季(気)で、少量とはいえ雨が雪になって降る小雪(しょうせつ)にあたりますが、それほど寒くありません。それに、東京では霜柱がほとんど見られなくなるなど、この数十年間に温暖になったと感じるのですが、気象学の立場からはいかがでしょうか。
木本さん―
最初に確認しておきたいのは、皆さんがご存じのとおり、天気は毎日変わります。雨が降る日もありますし、暖かい日も涼しい日もあります。また、夏の天気をとっても、少し暑い夏も少し涼しい夏もあります。自然の現象として、とくに大気の通り道が決まっていないために、気象には揺らぎがあるのです。扇風機の風の「1/f揺らぎ」【1】は、自然の揺らぎに近いもので、心地よさを感じさせます。それが気象本来の性質です。
ところが、数十年とか百年近い長期の気象データを調べますと、日本だけでなく、地球が温暖化していることが分かってきました。年によって寒さ・暖かさも少しずつ違うのですが、ならしてみると徐々に暖かくなっているのです。その原因が、人間活動に伴う温室効果気体の排出によることが、科学的に明らかになってきたのです。
一般の方々が、霜が降りる日が少なくなったと感じるような温暖化現象の多くは、気象学の研究で科学的に証明されています。ただし大都市では、温室効果気体による地球温暖化の影響と、アスファルトやビルが増えたことによる都市化の影響の両方が重なっています。東京の場合、年平均気温が100年間で大体3℃くらい上がったのですが、そのうちの1℃が温暖化の影響、残りの2℃が都市化の影響といえます。
大塚― 数十年という長い時間の中で、傾向を判断されるのですね。
木本さん― そうです。10年や20年、あるいは30年くらいですと、そのくらいの期間で気候に周期性のあることが最近分かってきました。1つの例をあげましょう。先ほど地球温暖化が進行中と申しましたが、細かく見ると、21世紀に入ってから気温上昇のペースが鈍っているのです。このことは、英語で停留を意味するハイエイタス【2】と呼ばれています。ところが、多くの研究の結果、ハイエイタスは自然界における数十年という周期的な気候変動の反映だったのです。その証拠に、海の表面の水温は上昇せずに停まっていたものの、深い海の水温は上昇を続けていたのです。ほかにも、北極の氷の変化や熱波の頻度の変化などから、温暖化は間違いなく進行しています。近々、世界気象機関から発表される今年の世界の平均気温も史上3位くらいに高くなりそうで、ハイエイタスはそろそろ終わったとみられます。
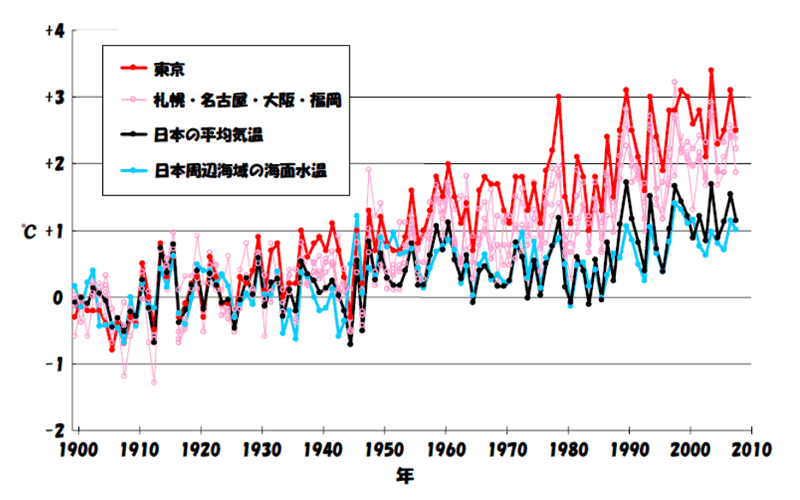
日本の大都市の気温、日本の平均気温、及び日本周辺海域の海面水温の推移。日本の平均気温は国内17 地点の平均。いずれも年平均値で、1901〜1930 年の30年平均値からの偏差を示す。(作成:気象庁;文部科学省・気象庁・環境省「日本の気候変動とその影響」(2009)より)
気象の揺らぎの中で、平均値からプラスあるいはマイナスに大きく外れる“異常気象”が時々起きることは異常ではない
大塚― ところで、異常気象という言葉が広く使われるようになってきましたが、ご専門の立場からはどのように捉えられていますか。
木本さん― 異常気象という言葉は、気象学者はあまり使いたくありませんでした。たとえば低頻度現象のように、頻繁には起きない珍しい現象という呼び方をしたかったのですが、そのような言葉ではインパクトがないこともあり、マスコミの方などが好む異常気象を使うようになったのです。
しかし大事なのは、異常気象といっても、正常か異常かいう意味での異常を指していないことです。地球温暖化があってもなくても、都市化があってもなくても、気象は揺らぐのです。揺らぎの中で、平均値からプラスあるいはマイナスに大きく外れること、すなわち異常気象が時々起きることは異常ではないのです。
大塚― 言葉の意味をちゃんと理解しないといけないですね。
木本さん― とはいえ、気象庁も異常気象の定義つくりを進め、大体30回に1回以下、30分の1以下の頻度で起きる現象を指すことにしています。30年に1回は起きるともいえます。そうすると、世界中にはもちろん30以上の地域がありますから、毎年のようにどこかで異常気象が起きてもいいわけです。
実際に問題になるのは、普通の状態ではなく地球温暖化などの影響が加わった場合でしょう。猛暑を例にとれば、普通の状態では30年に1回しか起きなかったような猛暑が、温暖化が進むにつれて、20年に1回、あるいは10年に1回の頻度で起きること、あるいは雨の場合にも、平均値から大きく外れる大雨の頻度が増えることが顕在化してきたといえます。
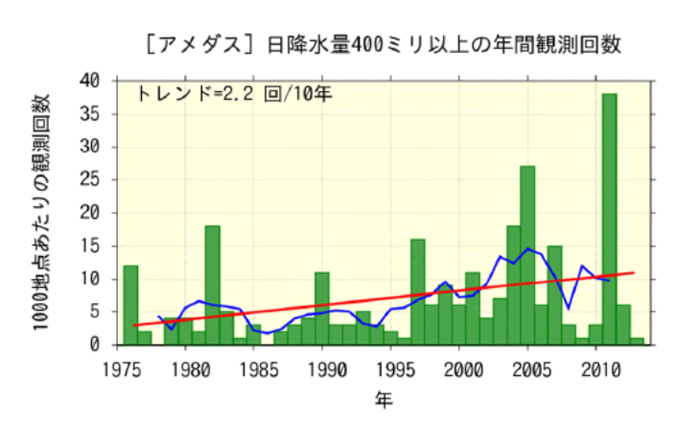
アメダス地点で日降水量が400mm以上となった年間の回数(1,000地点あたりの回数に換算)。青い折れ線は5年移動平均、赤い直線は信頼度90%以上の変化傾向を示す。(気象庁「異常気象レポート2014」)
大塚― 長期的にみた場合に、頻度が多くなっているということですね。
木本さん― そのとおりです。熱中症の患者さんが多く出る猛暑が起きたり、大雪が降ると、私のところに「温暖化のせいですか」と問い合わせがよくきたりします。温暖化とは数十年の長期傾向を指しているので、一回一回の猛暑や大雪の原因が温暖化というのはおかしいのです。一回一回の猛暑や大雪の原因は、その時その時の気圧配置、あるいはエルニーニョの状況によるのです。
とはいえ、温暖化の長期傾向の影響がないわけではないのですよ。私たちは、温暖化の影響を定量的に表す研究を進めています。異常気候の頻度や強さの変化に、温暖化などの要因が何%くらい寄与するかを明らかにするために、イベントアトリビューション【3】という方法を用いています。
複雑で大量のデータ処理が必要な検証ができるようになったのは、コンピュータの性能が格段に上がったことによる
大塚― イベントアトリビューションについて、基本的な考え方だけでもご説明いただけますか。
木本さん― 今述べた猛暑とか大雪というイベントに、それぞれの要因がどのくらい寄与したかを検証するのです。もちろん、温暖化は検証する要因の1つです。検証のポイントは、猛暑や大雪というイベントは自然の気候システムの中でも起きるので、その時の発生確率を求めておき、温暖化のような要因が加わった時のイベントの発生確率を求め、比較するのです。そのためには、数多くのサンプルが必要です。もし30サンプルしかなければ、30回に1回以下しか起きないイベントに、影響があったかどうか分かるはずもありません。同じ条件で100回のサンプル、条件を変えてまた100回のサンプルというように、何度も計算する必要があります。このように複雑で大量のデータ処理が必要な検証ができるようになったのは、コンピュータの性能が格段に上がったことによります。

2013年日本の猛暑のイベントアトリビューション。横軸は7-8月の日本の平均気温平年偏差、縦軸は確率密度(〜相対頻度)。赤線は、2013年条件の数値モデル実験で推定した確率密度分布。青線は2013年条件から温暖化分を差し引いた実験での分布、緑線は長期間(過去33年)の分布のモデル再現値。温暖化は2013年に観測される以上の猛暑の発生頻度を増加させる(青と赤の陰影を比較)。(Imada et al. (2014) Bull. Amer. Meteor. Soc. にもとづく)
大塚― 私たちがテレビなどでよく耳にする、偏西風やエルニーニョと異常気象との因果関係も、このようにして推測されているのですか。
木本さん― 日本の上空には季節を問わず偏西風が吹いており、その南側は暖かく北側が冷たくなっています。偏西風が蛇行すると通常は冷たいところが暖かくなるとか、暖かいところが冷たくなるので異常気象の多くは偏西風の蛇行と関係しています。蛇行が大きくなる、また長続きする原因が問題なのです。
偏西風の蛇行が長く続く大きな原因の一つに、エルニーニョ現象があります。エルニーニョとは、ご存知のように、太平洋の赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面の水温が高くなる現象で、海水温の上昇は1年くらい継続します。この海水温の変化が、熱帯の雲の活動を変え、広い範囲で大気の流れや気圧配置が変わるのです。
エルニーニョの影響は大きいですが、ほかにもいろいろな現象が知られており、気象要因の因果関係が十分解明されているかというと、まだまだ多くの問題が残されています。
温暖化の影響を解明し対策を考えるには、正確な初期値を与えた上で、1年先、5年先、10年先、20年先と連続的に予測することが有効
大塚― 多くの問題があるとしても、観測値に基づき要因間の関連性を推測しているということなのでしょうか。
木本さん― 観測にもとづいて推測し、その仮説を数値モデルを用いて、できる場合にはリアルタイムで検証しているのです。たとえば、8月の異常天候については、9月になるかならないうちに報道発表しますが、その内容にはごく短期間にリアルタイムで計算した結果も含まれています。以前とは違い、モデル計算で仮説検証まで迅速にできるようになってきたのです。
大塚― 温暖化による寄与も、このようにして検証されるのですか。
木本さん― そうです。問題は、どの現象に対する温暖化の寄与かですね。もし昨日の気温に対する温暖化の寄与であれば、毎日の気温は揺らいでおり大きく変わりますから、寄与はほとんどないことになるでしょう。しかし、30年間の気温の平均値を10年ずつずらして比較すると、寄与は大きくなるでしょうね。時間と空間のスケールによるわけで、時間が長くなるほど、空間が広くなるほど温暖化の寄与は増すのです。
大塚― 私たちは天気や気象の予報にとくに関心があるのですが、比較的短期の予報と長期の予報とでは、考え方や手法に違いがあるのでしょうか。
木本さん― 今、皆さんが見聞きされている天気予報には、週間予報もありますし、3か月先までの長期予報もあります。3か月先までの予報を含め、これらのほとんどすべてをコンピュータに計算させています。どのように計算させるかというと、世界中の気象台の観測データや人工衛星の観測データなど、ありとあらゆる観測データを集め、今現在の地球の大気の様子を診断し、それを初期値にして時間を先に進める形で計算させています。
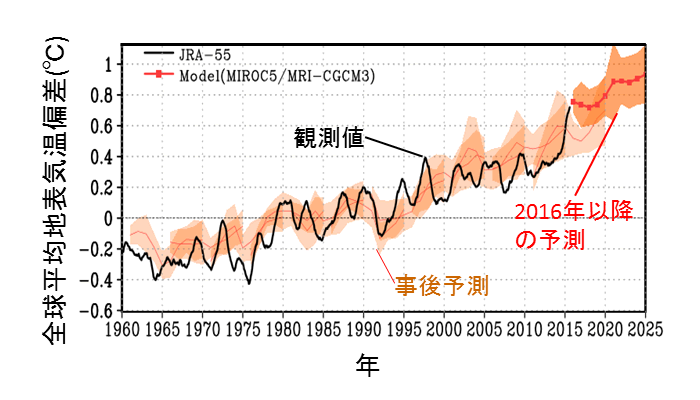
全球平均地表気温(1961-2010年平均からの偏差)の時系列。黒実線は観測値。1998年〜2013年の横ばい傾向をハイエイタスと呼んでいる。細い橙色の実線と陰影は、数値モデルによる事後予測とその不確実性幅。太い赤線と陰影は、2016年以降の予測とその不確実性幅。本図の予測は、研究目的の実験にもとづくもので公式のものではない。
大塚― そうすると、理論的にはその延長上に10年先も、何十年先も対象にできるということでしょうか。
木本さん― あまり先だと初期値の違いに意味がなくなってきます。予測する期間が長くなるほど誤差が大きくなり不確実性が増すのは、お分かりいただけると思います。たとえば、今日の気象を初期値として設定し、今日から始めて数年先あるいは数十年先の特定の日、たとえば1月1日の気象を計算させても、信頼できる答えは得られないでしょう。
温暖化の影響のような数十年先の予測は、その時点に対して予測される大気中二酸化炭素濃度などを用い、初期値とは関係なく計算されてきました。
しかし、温暖化の影響を解明し対策を考えるには、正確な初期値を与えた上で、1年先、5年先、10年先、20年先と連続的に予測することが有効なのです。実は最近、このような試みが世界気候研究計画【4】を中心に始まりました。まだ十分には満足できないとしても、10年先の温暖化の影響についても信頼に足る結果が得られ始めています。先ほどの、ハイエイタスの予測もこのような計算に基づいているのです。
過去の状況が説明できないようでは、100年先の予測を信用してもらえない
大塚― 新しい研究の流れをご説明いただきましたが、木本さんご自身は、どのようなことにとくに注目されていますか。
木本さん― 最初に申しあげたいのは、コンピュータの性能が飛躍的に向上し、気象モデルを用いる長期予報が行えるようになったことです。一方で、気象観測でも人工衛星が大活躍するようになってきました。30年前には思いもしていなかったことです。
数値モデルと観測を比べると、モデルは人がつくることから、観測の方が信用できると思われるかもしれません。しかし、観測は時間と空間を網羅するわけにはいきませんので、まばらにしか値が得られないという欠点もあるのです。観測とモデルにはそれぞれ長所と短所があるわけで、最近は、両者を融合し、地球の状態を時々刻々モニターしモデル分析する試みも始まっています。統合地球環境監視予測システムとも呼べるもので、このようなシステムができると、予報の精度がさらに向上するでしょう。
私は、気象観測データが短期間しかないことにも注目しています。気温や風速が「記録を更新しました」とよく報道されますが、50年程度しかデータの蓄積がないために、「頻繁に更新される」ともいえるのです。ところが、人工衛星のデータや海中での観測データは最近のものしかありませんが、地表の気温のデータや海の表面の水温のデータは150年くらい前からあるのです。これらのデータとモデルを組み合わせ、現在から時間を遡り、長期にわたる連続した変化として表すことも可能になってきました。私たちも挑戦しているところです。
大塚― 手間のかかる研究でしょうね。
木本さん― おもしろいですよ。19世紀のエルニーニョの「予報」ができるのですよ。1890年に、20世紀のエルニーニョに匹敵するエルニーニョがあったと言われているのですが、それを示唆する海水温のデータもあるのです。また、日本の軍隊は昔アジアの方々に申し訳ないことをしたのですが、旧海軍が観測した気象データは、気象学にとっては有力な情報です。世界中のデータを集め分析しようと考えています。というのも、過去の状況が説明できないようでは、100年先の予測を信用してもらえないでしょう。
大塚― そのような地道な研究が、先ほど言われた統合地球環境監視予測システムにもつながるのでしょうね。ところで、気象学者からの発信を私たちが受け取る時に注意すべきことなどをご指摘いただけますか。
木本さん― 2つのことを申し上げたいと思います。第1に、はじめに申し上げたように、異常気象という言葉は、正常か異常かという場合の異常ではないことです。気候は毎日そして毎年違うのです。第2に、温暖化について、多くの現象が温暖化に影響を受けます。降雨についてはとくに注意が必要です。温暖化により水蒸気量が増え降水現象が極端化しますから、降るときにはどっと降る傾向が強まる一方で、砂漠などではカラカラに乾いてしまうことも増えるのです。
大気中の二酸化炭素累積排出量と温度上昇はきれいに相関し、右肩上がりに並んでいる
大塚― 最後になりますが、木本さんからEICネットをご覧になっている読者の皆さまにメッセージをいただければと思います。
木本さん― 私の専門分野ではないのですが、地球温暖化を進行させている二酸化炭素をはじめとする温室効果気体の排出量が大変気になっています。IPCCが2013年に発表した第5次評価報告書(AR5)の第1作業部会の報告書に、1枚の新しい図があります。この図は、横軸に人間活動により排出された二酸化炭素の総量を、縦軸に産業革命前からの気温上昇をとったものです。二酸化炭素累積排出量と温度上昇はきれいに相関し、右肩上がりに並んでいます。このことはものすごく重要です。排出量が増加し続ければ気温も止まることなく続いてしまうのです。気温上昇を止めるためには人為排出量をゼロにしなくてはいけません。このグラフは大変きびしい事実をつきつけています。
今日私は猛暑の話をしましたが、2010年の日本の猛暑といっても、平年値より1.5℃高かっただけなのです。それも夏だけのことでした。それにもかかわらず、熱中症の患者さんの増加を含め大騒ぎでした。パリ協定が目指している2℃未満の上昇は、世界中で起きますし季節も問わないのです。このような状況について関係者は危機感をもっているのですが、一般に浸透していないように思われ、私はとても心配しています。少なくとも、温暖化が起こっているのかいないのか、あるいは温暖化は誰のせいかなど、そんな議論をしている場合ではないと感じます。
温室効果気体の排出量をなくすゼロエミッションに近づけるために、私たちはエネルギーをどうまかなうのか、人工光合成【5】のようなイノベーションが起きるのか、また、CCS【6】により二酸化炭素(炭素)を外部に出ないように封じ込められるのかなど、緊急に対処すべき難問が山積しています。私が理解している限り、これらの技術を含む温暖化防止への取組みがまったく不十分なままなのです。人類が英知を結集し、将来に希望がもてるような展開を願うばかりです。
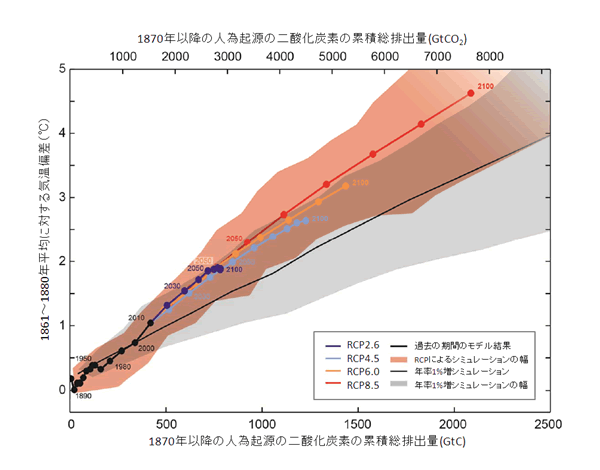
世界全体の二酸化炭素の累積総排出量の関数として示した、様々な一連の証拠による世界平均地上気温の上昇量。2100年までの各RCPシナリオ【7】について様々な階層の気候−炭素循環モデルから得られた複数モデルの結果を、色付きの線と10年平均(点)で示している。明確にするため、いくつかの10年平均にその年を示している(例えば、2050は2040〜2049年の10年平均を示す)。過去の期間(1860年から2010年)のモデル結果は黒で示されている。着色されたプルーム状部分は4つのRCPシナリオにわたる複数モデルの幅を表しており、RCP8.5シナリオにおいて利用できるモデルの数が減少すると共に陰影を薄くしてある。二酸化炭素を1年当たり1%ずつ増加させた場合(1%/年CO2シミュレーション)の強制力による、CMIP5モデルのシミュレーションにより予測された結果の複数モデル平均とその範囲は、細い黒線と灰色の陰影域で示されている。累積二酸化炭素排出量の特定の値に対して、二酸化炭素を1年当たり1%ずつ増加させたシミュレーションの結果は、二酸化炭素以外の追加的強制力を含んでいるRCPシナリオにより駆動されるものよりも低い温暖化を示している。気温は1861〜1880年の期間平均を基準としており、排出量は1870年を基準としている。各10年平均は直線で結んである。更に詳細な技術情報は、技術要約の補足資料を参照。(気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書政策決定者向け要約気象庁訳による)
大塚― 気象研究の現状と将来への展望について、いろいろな視点からお話しいただきました。最後に、地球温暖化の本質的な問題のご指摘をいただきました。木本さんのご指摘を多くの方々と共有したいと思います。本日は、ありがとうございました。

東京大学大気海洋研究所副所長・教授の木本昌秀さん(左)と、一般財団法人環境イノベーション情報機構理事長の大塚柳太郎(右)。
注釈
- 【1】1/f揺らぎ
- スペクトル密度が周波数fに反比例する揺らぎのことで、fは0より大きい有限な範囲をとる。ピンクノイズとも呼ばれ、自然現象でしばしばみられる。
- 【2】ハイエイタス(Hiatus)
- 米国大気研究センターが、全球的な平均気温の上昇率が横ばいあるいは低下傾向になる状態を指すために、2011年ころから用い始めた。具体的には、地上の平均気温が1880年から2012年に0.85℃上昇したものの、今世紀に入ってからは、二酸化炭素濃度が1年あたり2.1ppm上昇したにもかかわらず、気温が10年あたり0.03℃の上昇に止まっている現象。
- 【3】イベントアトリビューション(Event Attribution)
- 異常気候のような極端現象は、人為的な影響の有無にかかわらず気候システムの中で自然に生じ得るため、原因を特定のイベントに帰すことはできないが、イベントの発生確率は外力の変化によって変動すると予測されるので、人為的な強制によるイベントの発生確率の変化の程度を評価する分析法。
- 【4】世界気候研究計画(World Climate Research Program: WCRP)
- 気候の予測可能性および人間活動の気候への影響を評価するため、気候システム・気候プロセスの理解を発展させることを目的に1980年に創設された国際研究計画。その調整は、世界気象機関(WMO) が行っている。
- 【5】人工光合成(Artificial Photosynthesis)
- 自然界で植物が行う光合成を人工的に行うことで、地球温暖化防止に関しては二酸化炭素の排出抑制になると期待されるが、一部の技術が確立された段階である。
- 【6】CCS(Carbon Dioxide Capture and StorageまたはCarbon Capture and Storage、二酸化炭素回収貯留または炭素回収貯留)
- 化石燃料の燃焼で発生する二酸化炭素を分離・回収し、地質がもつ炭素貯留能力や海洋がもつ炭素吸収能力を活用し、大気から二酸化炭素を隔離する技術。日本を含む多くの国で取組みが開始されているが、安全性・信頼性に係る技術の検証に加え適地の選定や経費など、さまざまな問題も指摘されている。
- 【7】RCPシナリオ
- IPCCの第5次評価報告書における代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)で、「低位安定化シナリオ(将来の気温上昇を2℃以下に抑える)」「中位安定化シナリオ」「高位安定化シナリオ」「高位参照シナリオ(2100年における温室効果気体の最大排出量に相当し、排出量の増加がほとんど抑制されない)」を指す。
記事に含まれる環境用語
関連情報
- エコチャレンジャー(第56回)「弘前大学理工学研究科・野尻幸宏教授に聞く、地球温暖化における海の役割」
- エコチャレンジャー(第51回)「元・気候変動担当大使の西村六善さんに聞く、気候変動問題の解決に向けた方法論と今後の国際的な動向」
- エコチャレンジャー(第45回)「名古屋大学大学院環境学研究科の高村ゆかり教授に聞く、新たな枠組の策定が期待されるCOP21に向けた国際交渉への展望」
- エコチャレンジャー(第36回)「鬼頭昭雄 筑波大学生命環境系主幹研究員に聞く、近年注目を集めている気象の極端現象と地球温暖化の影響とその対策」
- エコチャレンジャー(第30回)「国立環境研究所社会環境システム研究センター・フェロー 甲斐沼美紀子さんに聞く、脱温暖化に向けた今後の対策」
- エコチャレンジャー(第24回)「三村信男・茨城大学地球変動適応科学研究機関長に聞く、地球温暖化への適応の現状と対策」
- エコチャレンジャー(第9回)「低炭素社会国際研究ネットワーク 西岡秀三事務局長に聞く、地球温暖化対策と政策策定に向けたプロセス」
この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。
なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。

