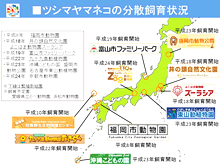No.222
Issued: 2013.07.05
希少種の違法取引にH25年7月2日から罰金1億円!(環境省自然環境局野生生物課保護増殖係)「種の保存法が改正されました」
法改正のお知らせチラシ
[拡大図]
先日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称:種の保存法)」が改正され、平成25年6月12日に公布されました。
この法律、なかなか日常生活では耳慣れないと思いますが、取引目的の捕獲や譲渡、生息地の開発・劣化等、人間の影響によって絶滅のおそれが生じている国内外の野生生物の種について、その保護や対策をするために平成4年に作られた法律です。
近年、絶滅危惧種の保全はますます重要な施策の一つになっていますが、今回、どんな内容の改正がされたのかをご紹介します。
種の保存法とは、どんな法律?

国際希少野生動植物種の「オオバタン」(オウムの一種)(写真:自然環境研究センター)

丸ごとの象牙も「器官」として、種の保存法の規制対象となる(写真:環境省)
種の保存法では、国内に生息する保護すべき種を「国内希少野生動植物種」として指定します。トキ、ツシマヤマネコ、ヤンバルクイナなど現在89種が指定されています。
また、主にワシントン条約の対象種など国際的に協力して保護をすることとされている種を「国際希少野生動植物種」として指定します(現在688分類群)。
指定することによって、国内での流通規制や、積極的な保護増殖事業の実施等の対象としています。
これらの「希少野生動植物種」は、普通はなかなかお目にかかる機会は少ない、いわゆる珍しい貴重な種ばかりです。でも、「国際希少野生動植物種」(のうちワシントン条約の対象種)は、意外なことにペットとしてお店で扱われていたり、インターネットで販売されていたりすることもあります。
ワシントン条約は国際取引(輸出入)を規制するものなので、日本国内で人工的に増やした個体や、ワシントン条約ができる前からすでに持っていた個体などは、環境大臣(登録機関)から登録票の交付を受ければ【1】、譲渡し等(売る、買う、無償であげる、もらうなど)ができるからです。
種の保存法の対象となるのは、生きている個体だけではありません。
- はく製や標本(種の保存法では「個体の加工品」といいます)
- 羽や毛皮などの部分(同じく「器官」といいます)
- 毛皮製品や装飾品など(同じく「器官の加工品」といいます)
も規制対象に含まれます。
改めて見てみると、人間によって価値が付けられ取引対象とされている「希少野生動植物種」は、人の生活に関係のあるところで様々な取り扱いがされていることがわかります。
罰則を大幅に強化
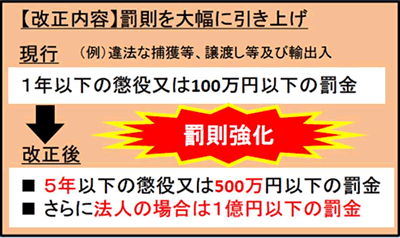
今回の法律の改正の一番の目的は、違法な取引や捕獲に対する罰則を大幅に強化しようというものです。残念なことに、これらの違法行為は後を絶ちません。
どれぐらい強化されたかといいますと、これまでは最高でも「1年以下の懲役又は100万以下の罰金」だったのが、「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と、実に5倍!になりました。さらに、ペット取引業者などにより組織的に違法行為が行われるケースが多いことを踏まえて、法人の場合は、なんと罰金が「1億円以下」となりました。
環境省の法律としても珍しい、高額の罰則です。類似の例では、比較的新しい法律である外来生物法が、平成17年の制定当初から1億円の罰金(法人)という規定を設けていました。今回はそれらの例も参考にし、できるだけ大幅な引き上げということで内容を固め、今回の改正となりました。
では、こんなに罰則を上げる必要があるほど、実際に違反をする人がいるのかという疑問があると思います。それが、いるのです。
これまでの違反の摘発事例では、遠くマダガスカルに生息するイニホーラリクガメという希少なカメ2匹が700万円で違法取引された例や、東南アジアに生息するスローロリス(ロリス属という原始的なサルの仲間)を1頭30万円前後で売買し、のべ60頭で1500万円もの利益を得ていた例などもみられます。

スローロリス。原始的なサル「ロリス属」の仲間。ペットとして人気があり、つい先日も違法売買が摘発された。(写真:自然環境研究センター)

イニホーラリクガメ。二匹で700万円という高額で違法売買され摘発された。現在は引き取られた動物園で飼育されており、見ることができる。(写真:自然環境研究センター)
これらは元々の生息地から密輸等によって日本に持ち込まれ、違法に売買されていたものです。摘発されて押収された個体は、ほとんどの場合、故郷に返ることはできず、引き取ってくれた動物園等で一生を過ごすことになります。
広告することも新たに規制対象に
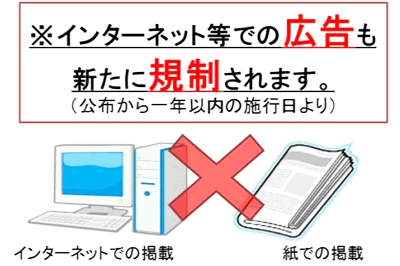
今回の法改正では、希少野生動植物種の売買に当たり、インターネットに掲載すること等についても、新たに「広告」の禁止ということで規制されることになりました。
ペットショップのホームページや、オークションサイトなどでは、たくさんの希少野生動植物種に関連する生体や製品が掲載されている例が見られます。
先に述べた適法なもの(※登録票の交付を受けたもの)は取引が認められていますが、それを証明する情報がきちんと掲載されていなければ、違法取引に関わるものとの区別がつきません。売る側だけでなく、買う側も、種の保存法では違反の対象になります【2】。
今後、広告は原則規制され、登録票がある場合には、その旨の明示などが義務付けられます。そうすることによって、より適正な流通管理ができるようになります。なお、この規制は、公布の日から一年以内に施行される予定です【3】。
保護増殖事業 〜国内の絶滅危惧種を保護する手段の一つ〜

ヤンバルクイナ。マングースの影響で絶滅が危惧されたが最近ではやや回復し推定約1500羽。(写真:環境省)
ここまでのお話は、主に流通する国際希少野生動植物種に関わるものですが、日本にいる国内希少野生動植物種も忘れてはいけません。佐渡での放鳥や巣立ちが今やすっかりニュースでもおなじみになったトキ、長崎県対馬にしかいないツシマヤマネコ、沖縄のやんばる地域に生息する日本で唯一の飛べない鳥ヤンバルクイナなど、バラエティ豊かな種がいます。
これらの種について積極的に保護・回復させる取組を行いやすくする改正が盛り込まれました。
種の保存法には保護増殖事業という制度があり、生態や生息数の基礎的な調査、生息環境の改善などの取組を実施しています。場合によっては飼育下において人の手で増やすことに取り組むこともあり、これを「生息域外保全」とよびます。万一に備えて保険的な意味で飼育下個体群を維持するほか、条件が整えば生息地に再導入や補強の形で野生復帰させることもあります。
生息域外保全(飼育下繁殖) 〜ツシマヤマネコの例〜

ツシマヤマネコ。長崎県対馬にのみ生息し、日本で最も絶滅のおそれの高いほ乳類の一つ。野生下では推定100頭以下。(写真:環境省)
ツシマヤマネコの飼育下繁殖は全国9つの動物園の協力で行われている。
[拡大図]
例えば、日本のほ乳類で初めて本格的な生息域外保全を実施しているツシマヤマネコの場合、(公財)日本動物園水族館協会の協力を得て、福岡市動物園を中心に全国9つの施設で保護増殖事業に参加していただき、30頭以上が飼育されています。
この取組を進めるためには、飼育下で安定的に飼育・繁殖し、順調に増やし続けることが必要ですが、一カ所で飼育できる数には限りがあるため、複数の場所で分散飼育を行います(万一の場合のリスク分散にもなります)。
そうすると、相性のよいペア作りなどのために動物園の間で個体の移動をすることがありますが、民間の動物園の場合は、これまでは個体ごとに環境大臣の許可がないと移動ができませんでした。書類手続に時間がかかり、迅速な対応がしにくい事情がありました。
そのため、今回の改正で特例に追加され、許可が不要となりました。手続が簡略化されることでスムーズな個体移動が可能になり、繁殖などが効果的に進むことが期待されます。
こうした生息域外保全は、ツシマヤマネコに限らず、トキやヤンバルクイナ、ミヤコタナゴなどの淡水魚、コシガヤホシクサなどの植物など多くの種類で行われています。今後、ますます重要性を増していく取組であり、また、動物園や水族館、植物園、昆虫館など、公的・民間を問わず、多くの専門施設の協力を得ないと実施できない取組でもあります。
今回の改正のように、制度面からも少しでも取組みやすい環境づくりをしていくことが重要です。
絶滅危惧種とは? 〜日本のレッドリストに掲載されている3597種〜
絶滅危惧種は、決して特別なものだけではありません。私たちの身近な環境から次々に姿を消している生きものも大変多くなっています。
昨年、環境省では第4次レッドリストを公表しました。ニホンカワウソが絶滅種(EX)に選定され、ウナギも絶滅危惧IB類(EN)という、上から二番目のランクに初めて評価されるなど、大きな反響を呼びました。絶滅危惧種として評価・選定(「指定」するわけではなく、規制などは伴いません)された生物は、全10分類群で3597種に及びます。
これらはほとんどが人間の活動に由来する要因によって減少し、特にランクの高い種は、種としての存続が心配されるほどの状況に追い込まれています。
いまだに、「きれいだから、珍しいから」といった理由で、捕獲や採集が主な影響要因となっている種も多くあります。さらに皮肉なことに、レッドリストに掲載されたり、ランクが上がったりすると、希少価値が高まり、捕獲・採集圧が一段と強くなってしまう例もあります。そんな人間の都合だけで、長い時間をかけて生きのびてきた生物の「種(しゅ)」が失われてはなりません。

レッドデータブック。レッドリストの掲載種について解説した本で、第4次レッドリスト対応の最新版を現在作成中。なお、レッドリストは種名のみを掲載したリスト。

ヤンバルテナガコガネ。沖縄本島北部のやんばる地域にだけ生息する日本最大の甲虫(カブトムシなどの仲間)。数がきわめて少なく、密猟されて高額売買の対象となっているといわれ、地元ではパトロールなどを実施している。(写真:環境省)
絶滅危惧種を守るということ
今回、法律が改正されたことで、絶滅危惧種をめぐる話題が普段よりも多くの注目を集める機会を得ることができました。今後、これを継続的な力として、これまで以上に取組を進めていくことが大切です。
一つでも多くの種が、今置かれている状況よりも良い状態に改善され、絶滅のおそれのある種が減っていくことを目指して、地域の方々、関係する団体、研究者、企業、都道府県や市町村など、多くの人たちがそれぞれできることを増やし、連携していくことが重要です。
皆さんもぜひ、自分にできることを考える機会を持ってもらいたいと思います。
環境省でもこれまで以上に、できることに取り組んでいきたいと考えています。
- 【1】登録票の交付
- 実際には登録票の交付事務は登録機関が代行しています(現在は(一財)自然環境研究センターが実施)。
- 【2】種の保存法の「譲渡し等」の違反の対象
- 種の保存法の譲渡し等の罰則は、有償・無償を問わないものであり、また売る・あげる場合だけでなく、買う・もらう側も同様に規制されます。さらに所有権を伴わない、貸す・借りる場合も規制対象です。
- 【3】広告規制の施行予定
- 広告規制の施行日は、これから政令で定めることになっています。
この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。
なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
記事・図版:環境省自然環境局 野生生物課 保護増殖係
※掲載記事の内容や意見等はすべて執筆者個人に属し、EICネットまたは一般財団法人環境イノベーション情報機構の公式見解を示すものではありません。